2025年 ベトナム(ハノイ・ホーチミン)及び日本物価比較調査レポート

2025年 主要都市間の生活費 全体比較
都市間の相対的な生活費水準を示す指標として、Numbeoの生活費指数(Cost of Living Index, ニューヨーク市=100)が参考になります。2025年のデータに基づくと、ベトナムの首都ハノイの指数は27.7から29.2の範囲にあり、経済の中心であるホーチミン市は30.5となっています。これに対して、日本の首都である東京は57.5と、ベトナムの主要都市と比較して著しく高い水準です。国全体の平均指数を見ても、ベトナムが約28.7であるのに対し、日本は約46.1と、両国間には大きな隔たりが存在します。
他の比較データも、この傾向を裏付けています。例えば、ベトナムの生活費は英国や米国の約40から50パーセント安価であるとされ、また東京の生活費はホーチミン市と比較して86.1パーセント高いという報告もあります。これらのデータは、ベトナムが日本、特に東京と比較して大幅なコスト優位性を持っていることを明確に示しています。
ベトナム国内の都市間で比較すると、ホーチミン市がハノイ市よりも一貫してわずかに高い指数を示しています。この背景には、ホーチミン市がベトナム最大の経済・商業の中心地であり、外国からの投資や高所得者層をより多く引きつけていることが考えられます。これにより、高級住宅や輸入品など特定のセクターにおいて価格が押し上げられている可能性があります。政治の中心であるハノイと比較して、経済活動の集中度が物価水準に影響を与えていると推察されます。
これらの指数はマクロ的な比較には有用ですが、個人の実際の支出はライフスタイルや消費パターンによって大きく変動します。例えば、ベトナムでは質素な生活を送れば月額500米ドル程度で生活可能との指摘がある一方で、より快適な生活を求めれば月額4,000米ドル以上になる可能性もあります。したがって、指数だけでは捉えきれない側面を理解するためには、具体的な費目ごとの比較が不可欠です。
生活必需品の価格差 詳細分析
住居費(家賃)

ベトナムにおける住居費は、都市やエリア、物件タイプによって異なります。首都ハノイでは、中心部にある1ベッドルーム(1BR)アパートの月額家賃について、複数のデータが存在します。一つの目安として300米ドル(約49,500円、約495万VND ※1USD=165JPY, 1JPY=165VNDで換算、以下同様)、あるいは860万VND(約52,000円)、または400米ドルから800米ドル(約66,000円から132,000円)という情報があります。中心部以外では月額570万VND(約34,500円)程度が相場とされます。スタジオタイプは月額300米ドルから600米ドル(約49,500円から99,000円)、2ベッドルーム(2BR)は月額600米ドルから1,500米ドル(約99,000円から247,500円)が目安です。ハノイ全体の一般的な家賃相場として月額330米ドル(約54,450円)というデータも見られます。
一方、ホーチミン市では、中心部の1BRアパートの月額家賃は平均で1,230万VND(約74,500円)、中心部以外では平均790万VND(約47,900円)とされています。1BRの家賃範囲としては、600万VNDから1,400万VND(約36,400円から84,800円)が一般的です。ホーチミン市全体の一般的な家賃相場は月額490米ドル(約80,850円)とされ、特に駐在員向けの1BRアパートは月額400米ドルから900米ドル(約66,000円から148,500円)の範囲で見られます。
日本の関東圏、特に東京では、家賃水準はベトナムと比較して大幅に高くなります。東京中心部の1BRアパートの月額家賃は平均で171,811円(約1,041米ドル)です。中心部以外でも平均91,168円(約553米ドル)となっています。面積が30平方メートル以下の物件では平均96,163円、単身者の平均家賃として128,000円というデータもあります。埼玉県は東京と比較すると家賃水準が低く、東京都の約78パーセント程度とされています。ただし、近年、埼玉県内でもエリアによっては家賃が前年比で10パーセント以上上昇したケースも見られます。関東地方全体の平均的な世帯支出(住居費を間接的に含む)は月額265,914円です。
分析すると、ベトナムの家賃は日本、特に関東圏と比較して劇的に安価です。東京中心部の1BR家賃は、ホーチミン市中心部の約2.3倍、ハノイ中心部の約3.3倍に相当します。驚くべきことに、東京の中心部以外の平均家賃でさえ、ハノイやホーチミン市の中心部の家賃と同等か、それ以上になる場合があります。埼玉県は東京よりは安価ですが、ベトナムの主要都市と比較すると依然として高額です。このため、日本からベトナムへ移住または長期滞在する場合、住居費は最も大きなコスト削減が見込める項目となります。ベトナムの両都市には月額300米ドルから400米ドル(約49,500円から66,000円)程度の非常に低価格な賃貸物件が存在し、これは予算を重視するデジタルノマドやリタイア層にとって魅力的な環境です。最低家賃水準が高い関東圏とは対照的です。一方で、ホーチミン市の家賃上限(例えば900米ドルや2,000万VND≒800米ドル)は、東京郊外の下限価格帯と重なる部分もあり、ホーチミン市内で高級賃貸市場が成長していることを示唆しています。
表1: 月額家賃比較(1ベッドルームアパート、2025年推定平均)
| 場所 | 現地通貨での家賃 | USD換算家賃 (約) | JPY換算家賃 (約) |
|---|---|---|---|
| ハノイ 中心部 | 8,600,000 VND | $330 | 52,000円 |
| ハノイ 中心部以外 | 5,700,000 VND | $220 | 34,500円 |
| ホーチミン市 中心部 | 12,300,000 VND | $470 | 74,500円 |
| ホーチミン市 中心部以外 | 7,900,000 VND | $300 | 47,900円 |
| 東京 中心部 | 171,800 JPY | $1,041 | 171,800円 |
| 東京 中心部以外 | 91,200 JPY | $553 | 91,200円 |
| 埼玉 (推定, 東京の78%) | 134,000 JPY | $812 | 134,000円 |
食料品・日用品

ベトナム(ハノイ・ホーチミン市平均)では、多くの基本的な食料品が日本よりも安価です。例えば、牛乳は約3.8リットル(1ガロン)で約140,000 VND(約850円)、食パンは約450グラム(1ポンド)で約24,000 VND(約145円)、白米は約450グラムで約10,600 VND(約65円)、卵は12個で約39,600 VND(約240円)、鶏むね肉は約450グラムで約42,100 VND(約255円)です。牛肉の赤身は約450グラムで約118,700 VND(約720円)と、これも日本より安価です。地元産のトマト、じゃがいも、玉ねぎなどの野菜は、1ポンドあたり約13,000から15,000 VND(約80円から90円)で購入できます。水は1.5リットルボトルで約12,900 VND(約80円)です。全般的に食料品は安価で、特に米、地元野菜、インスタント食品は日本より大幅に安い傾向にあります。ただし、ヨーグルトやサラダ油などの一部の加工食品や輸入品は、日本と同等か、場合によっては割高になることもあります。週の食料品費の目安としては、ローカル市場を中心に購入する場合は20米ドルから40米ドル(約3,300円から6,600円)、輸入品を多く扱うスーパーマーケットを利用する場合は50米ドルから100米ドル(約8,250円から16,500円)程度です。
一方、日本(関東/東京)では、同じ品目でも価格が異なります。牛乳は約3.8リットル換算で約908円(ただし、1リットルパックの価格帯が広いため、換算値も約830円から1,515円と幅があります)。食パンは約450グラム換算で約228円(1斤あたりの価格帯は97円から680円)。白米は約450グラム換算で約251円(1キログラムあたり790円から1,200円)。卵は12個換算で約318円(10個パックの価格帯は219円から681円)。鶏むね肉は約450グラム換算で約495円(1キログラムあたり約1,090円)。牛肉の赤身は約450グラム換算で約1,459円。地元産の野菜(トマト、じゃがいも、玉ねぎ)は、1ポンドあたり約186円から335円の範囲です(例:トマト1キログラム 1,326円から1,996円、じゃがいも1キログラム 558円から798円)。水は1.5リットルボトルで約127円です。関東のスーパーマーケット間でも価格差が見られます。東京での単身者の月間食費は、約60,000円や450米ドル(約74,250円)というデータがあります。
分析すると、食料品は全体的にベトナムの方が大幅に安価であり、特に米、パン、卵、鶏肉、地元産の野菜などは東京の半額以下であることが多いです。しかし、輸入品、乳製品(牛乳は種類や入手元によって価格差が小さいか、ベトナムの方が高い場合もある)、一部の加工食品については価格差が縮小、あるいは逆転するケースも見られます。牛肉はベトナムの方がかなり安価な傾向があります。ベトナムでは、スーパーマーケットだけでなくローカル市場を利用することで、さらに費用を抑えることが可能です。食生活がコストに与える影響は大きく、ベトナム産の食材を中心とした食生活を送れば食費は極めて低く抑えられますが、欧米や日本からの輸入品に頼る場合は、これらの特定品目については関東圏に近いコストがかかる可能性があります。これは、最大限の節約を目指す場合、現地の食材に適応する必要があることを意味します。母国の食生活を維持したい場合は、食費カテゴリーにおける金銭的なメリットは限定的になります。一部の加工食品の価格が日本と近いのは、輸入関税、特定品目における国内生産の非効率性、あるいはベトナム市場におけるブランドの価格設定戦略などが影響している可能性があります。
表2: 食料品バスケット価格比較(2025年推定平均)
| 品目 | ハノイ/HCMC 平均 (VND) | ハノイ/HCMC 平均 (JPY換算 約) | 東京 平均 (JPY) | 埼玉/関東 スーパー平均 (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 (1L) | 36,800 VND | 223円 | 240円 | 138-236円 |
| 食パン (500g) | 26,500 VND | 160円 | 245円 | 105-192円 |
| 米 (白米, 1kg) | 23,400 VND | 142円 | 571円 | 401-495円 (5kgベース換算) |
| 卵 (10個パック) | 33,000 VND | 200円 | 265円 | 204-267円 |
| 鶏むね肉 (500g) | 46,500 VND | 282円 | 545円 | 590-640円 (100gベース換算) |
| 牛肉 (赤身, 500g) | 131,000 VND | 794円 | 1,610円 | 1,285-1,610円 (100gベース換算) |
| トマト (1kg) | 30,400 VND | 184円 | 738円 | 1,326-1,996円 |
| じゃがいも (1kg) | 32,800 VND | 199円 | 410円 | 558-798円 |
| 水 (1.5Lボトル) | 12,900 VND | 78円 | 127円 | – |
交通費
ベトナムの交通費は、日本と比較して非常に低価格です。ハノイでは、公共交通機関の月間パスが約8米ドル(約1,320円)または200,000 VND(約1,200円)で購入でき、1回券はわずか8,000 VND(約50円)です。タクシーの初乗り運賃は約15,000 VND(約90円)、1マイル(約1.6km)あたりの運賃は約24,140 VND(約145円)です。バイクのレンタルは月額50米ドルから100米ドル(約8,250円から16,500円)で可能であり、Grabなどの配車アプリを利用した移動は1回あたり1米ドルから5米ドル(約165円から825円)程度です。
ホーチミン市でも同様に交通費は安価で、公共交通機関の月間パスは約337,500 VND(約2,050円)、1回券は約7,000 VND(約42円)です。タクシーの初乗り運賃は約16,750 VND(約100円)、1マイルあたりの運賃は約25,750 VND(約155円)です。バスパス2枚で月額16米ドル(約2,640円)という情報もあります。ガソリン価格は、1ガロン(約3.8リットル)あたり約88,000から90,500 VND(約530円から550円)です。
日本の東京では、公共交通機関の月間パスが約8,000円、1回券は平均214.50円(約1.3米ドル)です。タクシーの初乗り運賃は500円、1マイルあたりの運賃は約708円です。ガソリン価格は1ガロンあたり約681円(1リットルあたり約179円、約1.08米ドル)です。東京での単身者の月間交通費は約20,000円とされています。
分析すると、公共交通機関の運賃(1回券、月間パス)は、ベトナムの方が東京と比較して格段に安価です。タクシー料金も大幅に安く、初乗り運賃は約5分の1、距離あたりの運賃も約5分の1程度です。ガソリン価格もベトナムの方が若干安価です。ベトナムでは配車アプリが普及しており、非常に手頃な価格で移動手段を提供しています。また、バイクの所有やレンタルはベトナムでは一般的で、費用対効果の高い選択肢となっています。ベトナムにおけるバイク文化の普及と配車サービスの低価格化は、広範で効率的ですが高価な関東の鉄道網とは異なる都市交通の様相を呈しています。関東のシステムは長距離移動に優れていますが、ベトナムでは短距離の都市内移動において非常に柔軟かつ安価な選択肢が豊富にあります。この違いは、日々の通勤パターン、インフラ整備の必要性、さらには都市計画の優先順位(例えば、ベトナムにおけるバイク交通やそれに伴う環境問題への対応)にも影響を与えます。東京の月間パスが高価なのは、ハノイの比較的シンプルなバス・メトロシステムと比較して、そのネットワークの規模と複雑さを反映しています。
表3: 交通費比較(2025年推定平均)
| 項目 | ハノイ (VND/JPY換算 約) | HCMC (VND/JPY換算 約) | 東京 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 公共交通機関 1回券 | 8,000 VND / 50円 | 7,000 VND / 42円 | 215円 |
| 月間パス(通常価格) | 200,000 VND / 1,200円 | 337,500 VND / 2,050円 | 8,000円 |
| タクシー 初乗り運賃 | 15,000 VND / 90円 | 16,750 VND / 100円 | 500円 |
| タクシー 1kmあたり (推定) | 15,000 VND / 90円 | 16,000 VND / 97円 | 440円 |
| ガソリン 1Lあたり | 23,500 VND / 142円 | 23,800 VND / 144円 | 179円 |
光熱費
ベトナムでの光熱費も、日本と比較して低く抑えられています。ハノイでは、85平方メートルのアパートにおける基本的な光熱費(電気、水道、冷暖房、ゴミ処理など)の月額は約205万VND(約12,400円、約79米ドル)が目安です。ただし、電気代はエアコンの使用頻度によって大きく変動し、月額50米ドルから150米ドル(約8,250円から24,750円)になることもあります。水道代は月額5米ドルから15米ドル(約825円から2,475円)、調理用ガス代は月額10米ドルから20米ドル(約1,650円から3,300円)程度です。インターネット料金は非常に安価で、月額10米ドルから20米ドル(約1,650円から3,300円)、平均では約222,000 VND(約1,350円)です。携帯電話プラン(無制限データまたは10GB以上)も同様に安く、月額5米ドルから10米ドル(約825円から1,650円)、平均では約134,000 VND(約800円)です。
ホーチミン市でも、基本的な光熱費(85平方メートルアパート)は月額約196万VND(約11,900円、約75米ドル)と、ハノイと同程度です。インターネット料金の平均は約255,000 VND(約1,550円)、携帯電話プラン(10GB以上)の平均は約155,000 VND(約940円)です。別のデータソースによると、一般的な光熱費の内訳として、電気代が月額60米ドルから80米ドル(約9,900円から13,200円)、水道代が2米ドル(約330円)、ガス代が2米ドル(約330円)、インターネット代が11米ドル(約1,815円)、ケーブルテレビ代が7米ドル(約1,155円)、携帯電話代が3米ドル(約495円)という例もあります。小規模アパートの光熱費合計としては、月額約150万VND(約9,100円)という目安もあります。
日本の東京では、同程度の広さ(85平方メートル)のアパートにおける基本的な光熱費の月額平均は約26,584円(約161米ドル)です。インターネット料金の平均は月額4,868円(約30米ドル)、携帯電話プラン(10GB以上)の平均は月額3,812円(約23米ドル)です。平均的な世帯の光熱費合計は月額約19,000円、単身者の平均光熱費は約12,000円、通信費(インターネット、携帯電話含む)は約12,000円というデータもあります。日本はアジア太平洋地域で3番目に電気料金が高い国とされています。
分析すると、同程度の広さのアパートにおける基本的な光熱費は、ベトナムの方が東京の約半額程度です。特にインターネットと携帯電話の料金はベトナムが劇的に安く、多くの場合、東京のプランの3分の1から8分の1程度の価格で利用できます。ベトナムでは高温多湿な気候のため、エアコンの多用により電気代が想定以上に増加する可能性がありますが、基本的なコスト構造は依然として日本よりはるかに低くなっています。ベトナムにおけるモバイルデータ通信とインターネットの驚異的な低価格は、場所を選ばずに仕事をするデジタルノマドやリモートワーカーにとって大きな魅力であり、接続性の観点からも魅力的な拠点となっています。この低価格は、デジタルインフラを推進する政府の政策や、通信事業者間の激しい競争を反映している可能性があります。対照的に、日本の高い光熱費、特に電気料金は、全体的な生活費の高さに大きく寄与しており、エネルギー消費習慣にも影響を与えていると考えられます。
表4: 月額光熱費比較(2025年推定平均)
| 項目 | ハノイ/HCMC 平均 (VND/JPY換算 約) | 東京 平均 (JPY) |
|---|---|---|
| 基本光熱費 (85㎡/915 sq ft アパート) | 2,000,000 VND / 12,100円 | 26,600円 |
| インターネット (60 Mbps以上) | 238,000 VND / 1,440円 | 4,870円 |
| 携帯電話プラン (通話 + 10GB以上データ) | 145,000 VND / 880円 | 3,810円 |
旅行関連費用の比較
宿泊費(ホテル)
ベトナムの主要都市、ハノイとホーチミン市の間でホテル価格に大きな差は見られません。一般的なシティホテルやスタンダードクラスのホテルは、1泊1室2名利用で5,000円から20,000円前後が目安です。高級ホテルやリゾートクラスになると、20,000円から80,000円前後となります。より具体的なクラス分けでは、3つ星ホテルは1泊30万VND(約1,800円)から、ミッドレンジホテル(4つ星相当)は1泊90万VNDから250万VND(約5,400円から15,000円)、高級ホテル(5つ星相当)は1泊250万VND(約15,000円)以上が相場です。特筆すべきは、5つ星ホテルであっても1泊10,000円から15,000円程度で宿泊可能な場合があることです。バックパッカー向けのホステルであれば、1泊15万VND(約900円)から見つけることができます。3泊4日の旅行を想定した場合、ホテル代の合計は15,000円程度から考えられます。
一方、日本の東京では、ホテルの価格帯は非常に広範ですが、全体的にベトナムより高額です。最高級ホテル(例:ザ・リッツ・カールトン東京、マンダリンオリエンタル東京)では、1泊70,000円から150,000円以上が一般的です。高級ホテル(例:東京マリオットホテル、東京ステーションホテル)では、1泊43,000円から87,000円以上となります。中級のビジネスホテル(例:プリンスホテル、東急REIホテル、ワシントンホテル)では、1泊8,700円から34,000円以上が目安です。低価格帯のエコノミーホテルやゲストハウス(例:東横INN)では、1泊5,500円から10,000円以上となります。旅行サイトの検索結果を見ると、多くのホテルが2泊で1人あたり40,000円から45,000円(つまり1室1泊あたり40,000円から45,000円に相当)の価格帯で表示されることがあります。価格比較サイトでは、2025年5月の価格例として、ワシントンホテルが1泊8,700円、東京ステーションホテルが1泊54,700円などで表示されています。
分析すると、バジェットクラスからラグジュアリークラスまで、あらゆるクラスのホテルにおいて、ベトナムの方が著しく安価です。ベトナムの高級ホテル(5つ星)の価格帯は、東京の中級ホテル(3~4つ星)の価格帯よりも安いことがしばしばあります。ベトナムの低価格帯の宿泊施設(ホステル、ゲストハウス)は非常に手頃な価格設定です。これにより、旅行者は東京での宿泊費の数分の一の予算で、ベトナムで5つ星クラスの贅沢な滞在を体験することも可能です。ホテル費用のこの劇的な差は、ベトナムを価格重視の旅行者にとって非常に魅力的な目的地にしています。日本と比較して、同じ予算内でより長い期間滞在したり、より高い水準の宿泊施設を選択したりすることが容易になります。このコスト優位性は、ベトナムの観光産業の魅力に大きく貢献していると考えられます。手頃な価格で豪華な体験ができる可能性は、多くの旅行者にとって大きな魅力となり得ます。
表5: ホテル宿泊料金比較(1室2名1泊あたり、2025年推定平均)
| ホテルクラス | ハノイ/HCMC 平均 (VND/JPY換算 約) | 東京 平均 (JPY) |
|---|---|---|
| バジェット/ホステル | 250,000 VND / 1,500円 | 8,000円 |
| ミッドレンジ/3-4つ星 | 1,500,000 VND / 9,100円 | 25,000円 |
| ラグジュアリー/5つ星 | 3,500,000 VND / 21,200円 | 70,000円 |
外食費
ベトナムでの外食費も、日本と比較して大幅に安価です。ハノイでは、安価なローカルレストランでの食事は1食あたり約50,000 VND(約300円)です。中級レストランで2名が3コースの食事を楽しんだ場合、合計で約600,000 VND(約3,600円)が目安です。マクドナルドのようなファストフードのセットメニューは約131,000 VND(約790円)です。街角の屋台での食事はさらに安く、1食あたり1米ドルから3米ドル(約165円から495円)程度です。一般的な中級レストランでの1食あたりの費用は、5米ドルから15米ドル(約825円から2,475円)が目安となります。
ホーチミン市でも同様の傾向が見られます。安価なレストランでの食事は約56,250 VND(約340円)、中級レストラン(2名、3コース)は約600,000 VND(約3,600円)、マクドナルドのセットメニューは約122,500 VND(約740円)です。ローカルレストランでの一般的な食事は50,000 VND(約300円)以上、フォーやバインミーといった定番のローカルフードは4万VNDから6万VND(約240円から360円)程度です。市内のレストランでの食事は、一般的に25万VNDから70万VND(約1,500円から4,200円)の範囲です。中級レストランでの一人あたりの食事代は約20万VND(約1,200円)という目安もあります。週に5回の外食を含む娯楽費として、月額250米ドルから300米ドル(約41,250円から49,500円)というデータも見られます。
日本の東京では、外食費はベトナムよりかなり高くなります。安価なレストランでの食事は1食あたり約1,000円(範囲としては600円から1,500円、約6米ドル)が目安です。中級レストランで2名が3コースの食事をした場合、合計で約7,000円(範囲としては3,600円から11,000円)です。マクドナルドのセットメニューは約800円(範囲としては700円から900円、約4.8米ドル)です。
分析すると、屋台からレストランまで、あらゆるレベルでベトナムの外食は日本(東京)よりも大幅に安価です。特にフォーやバインミーなどのローカルな食事は、数百円で楽しむことができます。中級レストランも東京よりかなり手頃な価格設定です。マクドナルドのような国際的なファストフードチェーンでさえ、ベトナムの方が東京より若干安価な傾向があります。屋台は、極めて低価格な食事の選択肢を提供しており、ベトナムの食文化の重要な一部となっています。特に屋台やローカル食堂での食事の手頃さは、ベトナムの文化体験および旅行体験の中核を成しています。これにより、旅行者や居住者は、東京のように外食費がかさむことをあまり心配せずに、頻繁に外食を楽しむことができます。この違いは、日常の習慣や社会的な交流にも影響を与え、ベトナムではカジュアルな食事がより身近なものになっています。ベトナムの中級レストランの価格帯(1食あたり約825円から2,475円)は、東京の安価なレストランの価格帯(600円から1,500円)と一部重なっており、ベトナムの外食がいかに高い価値提案を持っているかを際立たせています。
表6: 外食費比較(1人あたり、2025年推定平均)
| 食事の種類 | ハノイ/HCMC 平均 (VND/JPY換算 約) | 東京 平均 (JPY) |
|---|---|---|
| 安価なレストランでの食事 | 53,000 VND / 320円 | 1,000円 |
| 中級レストランでの食事 (3コース) | 300,000 VND / 1,800円 | 3,500円 |
| ファストフードセット (例: マクドナルド) | 127,000 VND / 770円 | 800円 |
旅行者向けの市内交通
旅行者がベトナム国内を移動する際の交通費も非常に安価です。タクシーの初乗り運賃は、ハノイやホーチミン市でおおよそ15,000 VNDから17,000 VND(約90円から100円)です。タクシーのメーター料金は、1キロメートルあたり約0.50米ドルから0.70米ドル(約80円から115円)程度です。GrabやBeといった配車アプリを利用すれば、1回の乗車で1米ドルから5米ドル(約165円から825円)と、非常に手頃な価格で移動できます。さらに安価な選択肢としてバイクタクシー(セオム)があり、短い距離なら10,000 VND(約60円)程度から利用可能です。公共交通機関(バス、ハノイのメトロ)の1回券は7,000 VNDから8,000 VND(約42円から50円)と極めて安価です。観光客向けのアクティビティとして、例えばハノイの旧市街を巡るシクロ(自転車タクシー)ツアーは、40分程度で約30万VND(約1,800円)です。
日本の東京では、市内交通費はベトナムより大幅に高くなります。タクシーの初乗り運賃は500円です。距離あたりの料金も高く、1マイル(約1.6km)で708円(1kmあたり約440円に相当)です。電車や地下鉄の1回券は、距離にもよりますが、平均的には約214.50円です。
分析すると、旅行者にとって、タクシー、配車サービス、公共交通機関といったあらゆる形態の市内交通が、ベトナムの方が日本(東京)よりも大幅に安価です。特に配車アプリは、手頃な価格と利便性、価格の透明性を提供し、地点間の移動を容易にします。公共交通機関は極めて安いですが、路線網の網羅性や旅行者にとっての分かりやすさという点では、東京の鉄道ネットワークに劣る可能性があります。バイクタクシーは、ベトナム特有の非常に低コストな移動手段として、地元の人々だけでなく旅行者にも利用されています。ベトナムにおける配車アプリの普及と手頃な価格は、旅行者の短距離移動に大きな変化をもたらしたと言えます。これにより、以前の伝統的なタクシー利用で時折見られた価格交渉の手間や不確実性が減り、観光体験が向上しています。
土産物・ショッピング
ベトナムでは、地元産品や手工芸品などの土産物を非常に安価に入手できます。例えば、ベトナムコーヒーは1パックあたり29,000 VNDから70,000 VND(約170円から420円)程度です。高品質なチョコレートとして知られる「マルゥチョコレート」の小さいサイズは、66,000 VNDから77,000 VND(約400円から470円)です。刺繍が施されたポーチや巾着袋は、ベトナムでは約200円から500円程度で購入できますが、日本では同様のものが1,000円以上することがあります(フリマアプリなどでの価格帯は450円から1,000円程度)。伝統衣装のアオザイも、手頃な価格のものなら1,000円程度から見つけることができます(フリマアプリでの例)。プリントTシャツは約10万VND(約600円)程度(フリマアプリ価格550円から1,111円)。ローカルのスナック菓子は1パック25,000 VNDから40,000 VND(約150円から240円)です。特定のブランド品、例えばコルゲートのオプティックホワイト歯磨き粉は、ベトナムでは約260円程度ですが、日本のインターネット通販などでは2,000円以上することもあります。一般的な雑貨の価格帯としては、マグネットやストラップが200円から500円、陶器が500円から3,000円、刺繍製品が2,000円から5,000円、石鹸やキャンドルが500円から3,000円程度が目安です。
一方で、国際的なブランドの衣料品や靴に関しては、日本との価格差はそれほど大きくありません。例えば、リーバイス501ジーンズは、ベトナムでは約78万VNDから79万5千VND(約4,700円から4,800円)ですが、東京では約8,082円、あるいは6,700円、約45米ドル(約7,425円)といった価格が見られます。ZaraやH&Mなどのファストファッションブランドのサマードレスは、ベトナムで約68万VND(約4,100円)、東京で約5,778円または4,700円です。ナイキの中価格帯ランニングシューズは、ベトナムで約220万VNDから250万VND(約13,300円から15,100円)、東京で約9,490円です。革靴は、ベトナムで約200万VNDから220万VND(約12,100円から13,300円)、東京で約12,726円または12,300円です。
分析すると、刺繍製品、コーヒー、ローカルスナック、陶器、漆器などの伝統的な土産物や工芸品は、ベトナムで購入すると非常にコストパフォーマンスが高いです。コルゲートの歯磨き粉のような特定の日用品も、日本の輸入価格と比較して大幅な節約になります。しかし、リーバイス、Zara、ナイキといった国際的に展開しているブランドの衣料品や靴については、価格差が比較的小さく、東京と比較してわずかに安いか、同程度の価格である場合も見られます。これは、ショッピングでの節約効果が主に地元産品やローカルブランドに集中していることを示唆しています。この価格構造から、節約を重視する場合は、国際ブランドよりもベトナムのローカルブランドや市場、地元の小規模店で購入する方が有利です。掘り出し物を求める旅行者は、ショッピングモール内のグローバルチェーン店よりも、市場や地元のブティックなどに焦点を当てるべきでしょう。一部の国際的なファッションブランドの価格が日本とほぼ同等である背景には、輸入関税、流通コスト、あるいは地域による価格差を限定するグローバルな価格戦略などが考えられ、これらの特定の商品については「物価の安いアジア」というメリットが薄れています。
観光アクティビティ
ベトナムでの観光にかかる費用も、日本と比較して一般的に安価です。ハノイの例を見ると、主要な博物館や史跡の入場料は非常に手頃です。例えば、ホアロー収容所跡(Hoa Lo Prison Relic)は5万VND(約300円)、文廟(Temple of Literature)は3万VND(約180円)、ベトナム軍事歴史博物館(Vietnam Military History Museum)は4万VND(約240円)、ホーチミン廟(Ho Chi Minh Mausoleum、関連施設含む)は4万VND(約240円)、ホアンキエム湖の玉山祠(Ngoc Son Temple)は3万VND(約180円)です。人気の観光地であるハロン湾への日帰りツアーも、内容や催行会社によりますが、格安のものであれば約100万VND(約6,000円)程度から見つけることができます。映画館のチケット料金も安く、11万VNDから12万VND(約670円から730円)程度です。
日本の東京では、映画館のチケット料金は一般的に1,900円です。博物館やアトラクションの入場料は施設によって様々ですが、数百円で入場できるベトナムの施設と比較すると、一般的に高価になる傾向があります。
分析すると、ハノイをはじめとするベトナムの都市では、博物館や歴史的建造物への入場料が非常に安く、通常は数百円程度で済みます。ハロン湾への日帰りツアーのような人気アクティビティも、手頃な価格のオプションが存在します。映画鑑賞などのエンターテイメント費用も東京より安価です。これらのアトラクションやアクティビティの低コストは、ベトナムを訪れる旅行者が、日本を旅行する場合と比較して、限られた予算内でより多くの場所を見学し、多様な体験をすることを可能にします。これは観光のアクセシビリティを高める重要な要素です。
価格差の主要ポイント
これまでの比較を通じて、ベトナム(ハノイ、ホーチミン市)と日本(関東圏、特に東京)の間で、2025年においても顕著な価格差が存在する分野が明らかになりました。最も大きな価格差が見られるのは、住居費(家賃)です。東京中心部の家賃はハノイやホーチミン市中心部の数倍に達します。次に、市内交通費(タクシー、配車アプリ、公共交通機関)もベトナムが格段に安価です。外食費、特にフォーやバインミー、屋台料理などのローカルフードは非常に手頃な価格で楽しめます。地元産品や手工芸品などの土産物も、ベトナムでは非常に安価に入手できます。さらに、基本的な光熱費、とりわけインターネットと携帯電話の通信費は、ベトナムが劇的に安い水準にあります。
一方で、価格差が比較的小さい、あるいは逆転する可能性のある分野も存在します。具体的には、輸入品全般、国際的な有名ブランドの衣料品や靴(例:リーバイス、Zara、ナイキなど)、そして一部の加工食品や乳製品(例:ヨーグルト、特定の種類の牛乳)などが挙げられます。これらの品目については、ベトナムで購入しても日本と比較して大きな節約にならない、あるいは同等か割高になるケースもあります。
ベトナム国内では経済成長に伴う物価上昇が続いており、また為替レートの変動(特に近年の円安傾向)は日本人にとっての体感物価に影響を与えます。しかし、これらの要因を考慮しても、2025年時点での全体的なコスト比較においては、ベトナムの日本(特に関東圏)に対するコスト優位性は依然として非常に大きいと言えます。
ハノイ・ホーチミン市における生活費の歴史的変動(2010年頃から2025年)
ベトナム経済の成長とインフレ概観
ベトナム経済は、1986年に開始されたドイモイ(刷新)政策以降、目覚ましい発展を遂げました。かつて世界最貧国の一つであったベトナムは、この期間に急速な経済成長を達成し、中所得国の仲間入りを果たしました。一人当たりの実質GDPは大幅に増加し、貧困率は劇的に低下しました。この経済成長は、国民の生活水準の向上(健康、教育へのアクセス改善、インフラ整備など)をもたらしましたが、同時にインフレ圧力も生み出してきました。
近年の経済動向を見ると、新型コロナウイルスのパンデミック後も力強いGDP成長が続いています。例えば、2022年の第3四半期には前年同期比でプラス13.67パーセント、同年最初の9ヶ月累計ではプラス8.83パーセント(これは2011年以降で最高の伸び率)を記録しました。消費者物価指数(CPI)の上昇率、すなわちインフレ率は、政府によってある程度抑制されつつも、持続的に上昇しています。年平均のインフレ率は、2022年が3.15パーセント、2023年が3.3パーセントでした。2024年に入っても物価上昇傾向は見られ、5月には前年同月比でプラス4.44パーセント、10月はプラス2.89パーセント、11月は前月比でプラス0.13パーセントと報告されています。2024年の1月から10月までの期間の平均CPI上昇率は、前年同期比でプラス3.78パーセントでした。直近の2025年第1四半期のCPI上昇率は、前年同期比でプラス3.13パーセントとなっています。国際通貨基金(IMF)は、2025年のベトナムのインフレ率を2.9パーセントと予測しています。米連邦準備制度理事会(FRED)のデータは、2025年を3.46パーセントとし、その後2029年まで年率3.4パーセント前後で安定すると示唆しています。また、労働者の生活水準向上と消費刺激策の一環として、2024年7月には地域別の最低賃金が平均で6パーセント引き上げられました。
ベトナムの急速な経済発展は、特にハノイやホーチミン市のような大都市部において、必然的に生活コストを押し上げる要因となります。インフレ率は比較的安定して管理されていますが、一貫した上昇傾向は、かつての「超格安」というベトナムのイメージが徐々に変化しつつあることを示唆しています。日本のような先進国に対するコスト優位性は依然として大きいものの、生活費の絶対額で見ると、その差は過去と比較して徐々に縮小していると言えます。
消費者物価指数(CPI)の長期推移
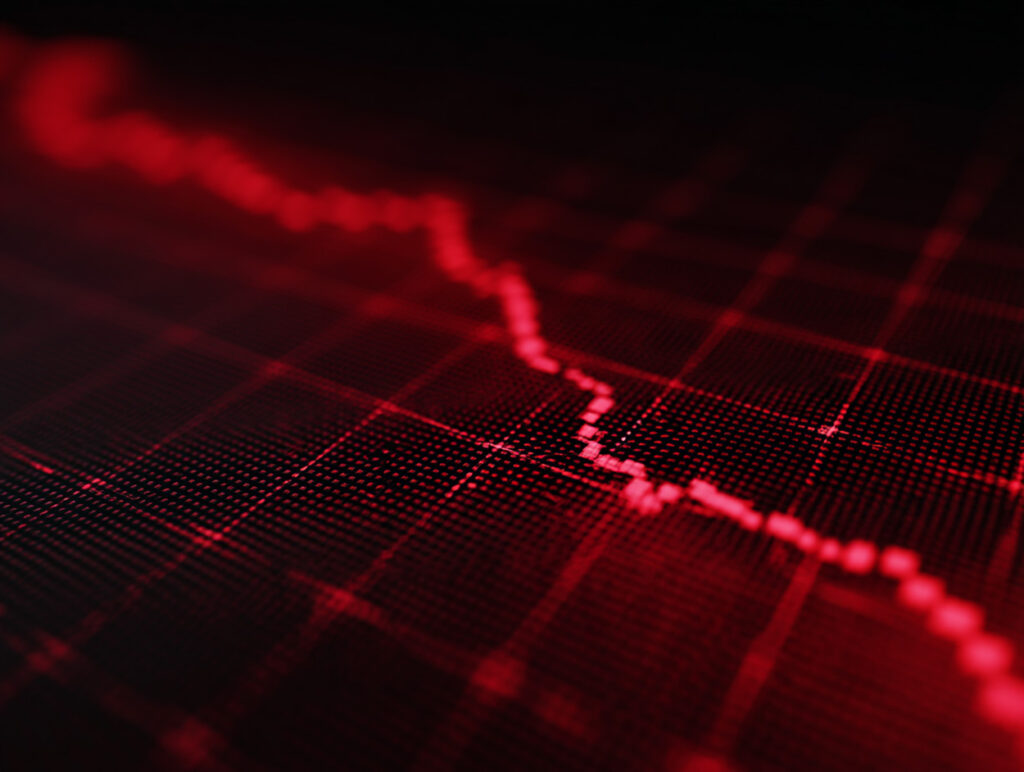
ベトナムの消費者物価指数の推移を分析するために、ベトナム統計総局(GSO)、世界銀行、国際通貨基金(IMF)などの公的機関が発表しているデータが利用されます。
世界銀行のデータによると、2010年を基準値100とした場合、ベトナムの消費者物価指数(CPI)は、2023年には183.1まで上昇しています。これは、2010年から2023年までの間に、消費者物価全体が平均して約83パーセント上昇したことを意味します。
年間のインフレ率(前年比CPI上昇率)を見ると、その変動がより明確になります。入手可能なデータに基づくと、2011年には18パーセントを超える高いインフレ率を記録しましたが、その後は徐々に落ち着き、2012年は約9パーセント、2013年は約6.6パーセント、2014年は約4.1パーセントとなりました。2015年には約0.6パーセントと非常に低い水準になりましたが、その後は再び上昇し、2016年から2019年にかけては年率2.7パーセントから3.5パーセントの範囲で推移しました。パンデミックの影響を受けた2020年は3.2パーセント、2021年は1.8パーセントと比較的低めでしたが、2022年は3.15パーセント、2023年は3.3パーセントと再び上昇しました。2024年の推定値は約3.8パーセント、2025年の予測値は各機関によって異なりますが、おおむね2.9パーセントから3.5パーセントの範囲とされています。
ベトナム統計総局(GSO)は、月次および四半期ごとの詳細なCPIデータを提供しており、地域別(都市部、農村部など)や品目別(食品、住宅、交通、教育など)の内訳も含まれています。これにより、物価変動の要因をより詳細に分析することが可能です。例えば、直近の2025年3月のCPIは、燃料や米の価格が下落した影響で前月比ではマイナス0.03パーセントとなりましたが、前年同月比ではプラス3.13パーセントと、依然として上昇基調にあることが示されています。GSOは、価格変動の大きい品目を除いたコアインフレ率の動向も追跡しています。
これらのデータから、2010年以降、ベトナムの消費者物価全体が大幅に上昇していることが確認できます。2010年代初頭には非常に高いインフレ率の時期がありましたが、その後はより穏やかな水準ながらも、一貫して物価上昇が続いていることがわかります。
表7: ベトナム 年間平均CPI上昇率(前年比、%)
| 年 | 上昇率 (%) | 年 | 上昇率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 18.6 | 2019 | 2.8 |
| 2012 | 9.1 | 2020 | 3.2 |
| 2013 | 6.6 | 2021 | 1.8 |
| 2014 | 4.1 | 2022 | 3.2 |
| 2015 | 0.6 | 2023 | 3.3 |
| 2016 | 2.7 | 2024 (推定) | 3.8 |
| 2017 | 3.5 | 2025 (予測) | 2.9-3.5 |
| 2018 | 3.5 |
特にGSOが提供する品目別のCPIデータは、どのセクターが全体のインフレを牽引しているかを理解する上で重要です。例えば、2022年には、世界的な燃料価格高騰の影響を受けた交通費や、教育関連費が大幅に上昇した一方で、郵便・通信費は技術進歩や競争激化により下落しました。食料・飲料費も顕著な上昇を見せました。このように物価上昇は一様ではなく、家計の消費パターンによってその影響度合いは異なります。世界の燃料価格、政府の教育政策の変更、国内の食料供給状況といった特定の要因を理解することは、将来の物価トレンドを予測する上で不可欠です。
主要費目におけるコスト変動の分析
2010年頃から2025年にかけてのベトナムの生活費上昇は、費目によってその度合いが異なります。
住居費: 日本と比較すれば依然として安価であるものの、特に外国人駐在員が多く居住するエリア(例えば、ハノイのタイホー区やホーチミン市の2区、7区など)の家賃は、国内外の富裕層や駐在員からの旺盛な需要により、2010年以降大幅に上昇したと考えられます。都市開発が進み、新しい近代的なアパートメントが増加したことも、家賃水準の上昇に寄与しています。
食料品: 米や野菜などの地元産の主要食料品の価格は、全体的なインフレに伴って上昇していますが、日本などと比較した際の相対的な手頃さは、他の費目に比べて維持されている分野と言えるでしょう。一方で、輸入品(乳製品、果物、加工食品など)の価格は、世界的なサプライチェーンの問題や輸送コストの上昇、為替レートの変動などの影響を受け、より急激に上昇した可能性があります。
交通費: 国際的な原油価格の変動は、ガソリン価格を通じて国内の交通費に直接的な影響を与えます。一方で、ハノイでのメトロ(都市鉄道)の部分開業や、Grabをはじめとする配車サービスの普及と競争激化は、10年、15年前と比較して、新たな移動手段を提供し、特定の交通手段のコストを安定させる、あるいは相対的に低下させる効果をもたらした可能性があります。
光熱費: インターネットや携帯電話などの通信費は、技術進歩と通信事業者間の競争により、サービス内容が向上しつつも、実質的な価格は非常に低い水準を維持、あるいは低下した可能性が高いです。これは、世界的なエネルギー価格の上昇傾向にある電気代やガス代とは対照的な動きです。
結論として、ベトナムにおけるコスト上昇の構造は一様ではありません。フォーを一杯食べたり、ローカルバスに乗ったりといった基本的な日常生活を送る上でのコストは、依然として手頃な価格を維持しています。しかし、国際基準のサービス(特定の高級住宅、輸入品、インターナショナルスクール、高度な医療など)を利用するためのコストは、過去15年間でベトナム国内において相対的にかなり高価になったと考えられます。これは、ベトナム経済が世界経済への統合を深め、国内の所得水準が向上したことの自然な結果と言えます。
生活費変動の背景要因
ベトナムにおける生活費の変動、特に上昇傾向には、複数の要因が絡み合っています。
- 経済成長: 持続的な高いGDP成長率は、国民所得の増加を通じて国内需要を刺激し、賃金水準を押し上げ、結果として全体的な物価水準の上昇圧力となります。
- インフレ: 国内需要の増加、サプライチェーンのボトルネック、国際商品価格の上昇、政府の金融政策など、様々な要因が複合的に作用して国内のインフレを引き起こします。
- 都市化と開発: 地方からハノイやホーチミン市のような大都市への人口流入が進む都市化は、都市部における住宅や各種サービスへの需要を急増させ、地方と比較して都市部の生活コストを不均衡に押し上げる要因となります。インフラ開発も物価上昇に影響します。
- 外国直接投資(FDI)と駐在員の需要: 外資系企業の進出拡大とそれに伴う外国人駐在員やその家族の流入は、特定のタイプの住宅(サービスアパートメント、高級コンドミニアム)、インターナショナルスクール、輸入品、西洋風レストランなどへの需要を高め、これらの特定の市場セグメントにおいて価格上昇圧力を生み出します。
- 国際商品価格の変動: ベトナム経済も、エネルギー(原油、天然ガス)や食料(穀物、食肉)など、国際市場で取引される商品の価格変動の影響を受けます。これらの価格上昇は、輸入コストの増加を通じて国内物価に波及します。
- 為替レートの変動: ベトナムドン(VND)の為替レート、特に主要貿易相手国通貨である米ドルや日本円に対する変動は、輸入品の国内価格や、外国人訪問者・居住者にとっての体感物価に直接的な影響を与えます。例えば、近年の円安・ドン高の進行は、数年前と比較して、日本人にとってはベトナムの物価が相対的に高く感じられる要因となっています。
今後の展望と考察
本レポートの分析結果をまとめると、2025年時点において、ベトナムの主要都市(ハノイ、ホーチミン市)は、日本の関東圏(特に東京)と比較して、依然として大幅な生活コストの優位性を持っています。この差は特に、住居費(家賃)、ローカルフードを中心とした外食費、市内交通費において顕著です。ベトナム国内では、経済の中心であるホーチミン市が首都ハノイ市よりもわずかに物価が高い傾向が見られます。同様に、日本では首都圏の中でも東京が埼玉などの周辺県よりもはるかに物価が高くなっています。
歴史的な推移を見ると、ベトナムの生活費は、継続的な経済発展に伴い2010年頃から着実に上昇してきました。しかし、その上昇ペースは管理されており、国際的な基準や日本の基準から見れば、依然として非常に手頃な水準にあると言えます。
2025年以降の展望としては、IMFやFREDなどの国際機関の予測(年間インフレ率2.9%~3.5%程度)に基づけば、ベトナムの生活コストは引き続き緩やかに上昇していくと予想されます。日本人にとっての相対的なコスト感は、今後の日本円とベトナムドンの為替レートの動向にも大きく左右されるでしょう。日本国内でもインフレは進行していますが、そのペースが今後鈍化する可能性も指摘されており、両国間の物価差が将来どのように変化していくかは注視が必要です。
考察:対象者別ポイント
居住者・移住者向け: ベトナムは、生活コストを大幅に削減できる可能性を秘めた移住先です。ただし、そのメリットを最大限に享受するには、現地のライフスタイル(ローカルフードの活用、ローカル市場での買い物、バイク移動など)にある程度適応することが鍵となります。住居の選択(エリア、物件タイプ)と消費パターン(ローカル品を重視するか、輸入品を多用するか)が、月々の支出に大きく影響します。ホーチミン市を選択する場合は、ハノイ市よりも若干高い生活費予算を見込む必要があるでしょう。
旅行者向け: ベトナムは、旅行者にとって卓越したコストパフォーマンスを提供します。日本への旅行と比較して、大幅に低い予算で同等以上に快適な、あるいはより豪華な旅行を楽しむことが可能です。宿泊費、食費、交通費が安いため、同じ予算でも滞在期間を延ばしたり、より多くのアクティビティを体験したりできます。最大限の費用対効果を求める場合は、高級輸入品店でのショッピングよりも、ローカルフードを楽しみ、現地の交通手段を活用し、地元産の手工芸品などを土産物として選ぶことが推奨されます。
全体的な留意点として、日本とベトナムの間の生活コストの差は依然として大きいものの、ベトナムの継続的な経済発展、それに伴う物価上昇、そして為替レートの変動といった要因を考慮すると、両国間の相対的な手頃さについては、将来にわたって固定的なものと考えず、定期的に最新の情報を確認し、見直していく必要があります。